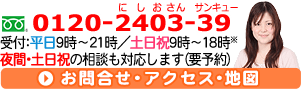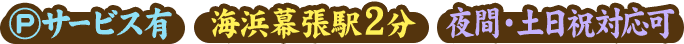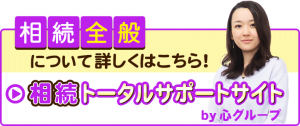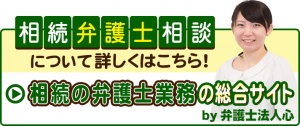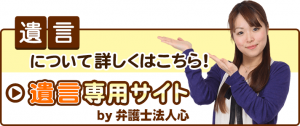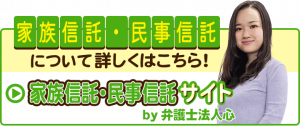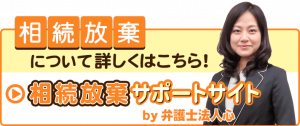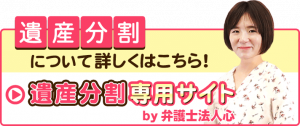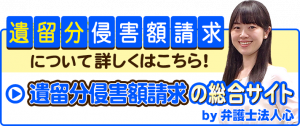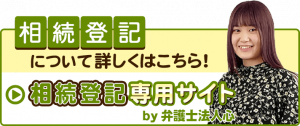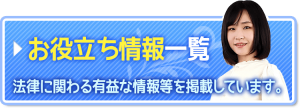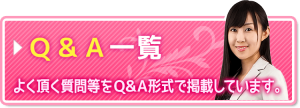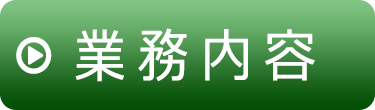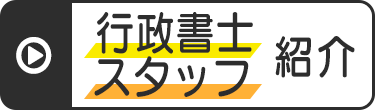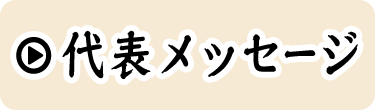遺産整理とは?遺品整理との違い
1 遺品整理について
まず、遺品整理について説明します。
一般的に遺品整理とは、亡くなった方(被相続人)がご生前に使っていた日用品や家具、衣類、思い出の品などを整理、処分する作業を指します。
主な目的は、住居の明け渡しや、後に住む相続人が使用できる状態にすることです。
遺品整理は相続の法律手続きとは直接関係はなく、具体的には以下のような作業を行うことが想定されます。
① 衣類や日用品、家具、家電などの家財道具の処分
② アルバムや写真、手紙など思い出の品の保管や仕分け
③ 遺産整理でも用いる財産関連の資料や価値の高い財産の仕分け
④ 家屋の清掃や原状回復
遺品整理は、相続人の方などが自ら行うこともありますが、時間や労力の負担が大きいこともあるため、専門の遺品整理業者に依頼するケースも多く見受けられます。
2 遺産整理で行うこと
遺産整理は相続の実務において使用される用語のひとつであり、一般的には相続人の調査、相続財産の調査、相続人への相続財産の引継ぎといった一連の法的および事務的な手続きや作業のことです。
遺品整理は、主に物品の片付けを行うものであるのに対して、遺産整理は相続財産の承継を主な目的としています。
遺産整理で行う主な作業は次のとおりです。
① 相続人調査・相続財産調査
② 遺産分割協議書作成
③ 相続税申告
④ 相続登記
⑤ 預貯金や有価証券の名義変更
これらの作業は複数の法律分野にまたがっていることに加え、取り扱うことができる専門家が限定されているものもありますので、弁護士、司法書士、税理士などの専門家が連携して対応するケースも多くあります。
3 相続人調査・相続財産調査
⑴ 相続人調査
遺産整理で初めにするべきことは、相続人を正確に確定させることです。
相続に関する手続きは、多くの場合遺産分割協議が済んでいることが前提となります。
そして、遺産分割協議は、相続人全員で行わないと無効になってしまいます。
そのため、相続人調査はとても重要な作業として位置付けられます。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得します。
代襲相続が発生している場合には、被代襲者(被相続人よりも先に亡くなっていた、本来相続人になるはずであった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も取得する必要があります。
⑵ 相続財産調査
相続人調査と並行して、被相続人の財産と債務を漏れなく調査する必要があります。
相続財産の調査に抜け漏れがあると、遺産分割協議を再度行わなければならなくなることや、相続税申告の際に申告漏れを起こすことがあるなど、トラブルにつながるおそれがあります。
調査の対象となる代表的な相続財産としては、現金・預貯金、有価証券(上場株式や投資信託)、不動産などが挙げられます。
被相続人が会社経営に携わっていた場合などにおいては、非上場株式が存在することもあります。
また、生命保険金は相続税の課税対象となることがあるため、金額を確認しておく必要があります。
4 遺産分割協議書作成
相続人と相続財産の調査が済みましたら、どの財産をどの相続人が取得するかを話し合います。
これを遺産分割協議といい、その結果を記した書類が遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、預貯金や有価証券の名義変更・解約、不動産の相続登記、相続税申告など、様々な手続きで使用します。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名と押印をします。
実務においては、押印には実印を用い、各相続人の印鑑証明書を添付します。
5 相続税申告
相続税は、相続開始を知った日(一般的には、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に申告と納付をしなければなりません。
相続税申告と納付は、基本的には相続財産の評価額が、基礎控除額を超えている場合に必要となります。
基礎控除額の計算式は次のとおりです。
3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
相続税申告における財産の評価はとても複雑です。
特に、土地と非上場株式は、評価の仕方次第で評価額が大きく変わる可能性があります。
また、民法上は相続財産には含まれない生命保険金や死亡退職金も相続財産にみなされるほか、これらには一定の非課税枠が設けられているなど複雑な計算が伴います。
評価を誤ると、過大な相続税を支払ってしまうことや、過少申告によるペナルティが課せられてしまう可能性があります。
相続税申告や納付は、期限を過ぎてしまうと延滞税や無申告加算税が課されてしまうため、できるだけ早く準備を開始することが大切です。
6 相続登記
被相続人が不動産を保有していた場合、相続人に名義変更を行う必要があります。
2024年4月からは、相続登記が義務化され、基本的には自己のために相続の開始があったこと、かつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければなりません。
相続登記の際には、相続登記申請書のほか、遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書、登録免許税などを管轄の法務局に提出します。
7 預貯金や有価証券の名義変更
被相続人の預貯金や有価証券を相続人が取得するためには、銀行や証券会社等で相続手続きを行う必要があります。
引き出しや解約、名義変更をするためには、遺産分割協議書、戸籍謄本などのほか、銀行や証券会社等所定の書類を作成して提出する必要があります。
銀行や証券会社等によって手続きの進め方が違うことがありますので、事前に問い合わせるなどしてしっかりと確認することが大切です。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒261-7107千葉県千葉市美浜区
中瀬2-6-1
ワールドビジネスガーデン マリブイーストタワー7F
0120-2403-39